 メニュー  ゲストETXギャラリー  アンケート結果ピックアップ 持っている望遠鏡は?(結果上位10位) | ETX-70AT | 41票 | | ETX-125 | 34票 | | ETX-105 | 33票 | | ETX-90 | 21票 | | LX200GPS | 21票 | | LX90 | 18票 | | LX200 | 14票 | | LXD55/75 | 13票 | | DS-2000 | 7票 | | RCX400 | 1票 |
アンケートトップ 管理者承認待ち システム管理
ニュース
ゲストETXギャラリー
ダウンロード
リンク
|
 |
ETXシリーズの概要を知るために
ETXってどんな望遠鏡?
Meadeの天体自動導入望遠鏡ETXシリーズの特徴や歴史など |
そして、相場を手早く見るようまとめてみた価格参考はこちら(2004年11月現在)。
ETXシリーズは、米国の望遠鏡2大ブランドの1社「Meade」(ミード)の製品です。同社は,コンピュータ制御天体望遠鏡の先駆者であり、どちらかというと光学性能に忠実なCelestron(セレストロン)と肩を並べる存在です。また、ETXは米Questarの「Questar
3.5」を基としたデザインだと言われています。
いちばんの特徴は、コンピュータユニット(本体からケーブルでつながる手のひらサイズの「オートスター」)により、2種類の駆動モーターを制御して全天の星を「自動導入」、そして「自動追尾」ができる点です。ただし、天体自動導入のためにはETX-ECモデルに加え、オプションのコントローラ「オートスター」を加える必要があります。ただし、2003年現在、末尾がATで終わる型番(例:ETX-90AT)は、オートスター標準同梱モデルです。このため、1999年からの末尾ECモデルは無くなっていく傾向にあり、国内でも2003年12月現在、製品名の末尾ECJとして同梱モデル名が継続販売されています(これまでの全モデル名リストは、後の方に載せています)。以降は、米国本土に習い、国内でもATになると予想されます。
天体自動導入可能なETXシリーズは5モデル
(2001年11月現在) Copylight(C)
Meade Inc. Photo by Meade.com |

左:ETX-90EC,中央:ETX-105EC,右:ETX-125EC
|

上側:ETX-70AT
下側:ETX-60AT(国内正式未発表) |
|
口径それぞれ90/105/125mmのマクストフカセグレン光学系モデル
|
口径それぞれ70mm,60mmの屈折光学系モデル |
|
どんなものか手っ取り早く知りたい場合には…、「自動導入」、「オートスター」のキーワードを追いかけてみてください。概要は、下にある解説「ETX-EC(AT)シリーズのおもな特徴」、そしていちばん上の「使い勝手を紹介」画像見出しの下、各モデルのインプレッションをご覧いただければよいかと思います。不明な点は、左メニュー「お問い合わせ」から質問くだされば、可能な限りお答えもします。
また、筆者はNexStar5(セレストロン)も所有しています。その購入決意から観望までなどは、姉妹サイト「Yoshi's
NexStar Site」に記しています。
■天体自動導入というキーワード
| 自動導入望遠鏡ってなに?「観る楽しみ」を味わえる望遠鏡です |
ETXのETは,Everybody's Telescopeの略で,「誰にでも簡単に使える望遠鏡」という意味を込めてつけられたそうです(Xは何だろう?)。
この意味の通り,ETXはセットアップ時に基準星となる星さえ微調整すれば,あとはコントローラからの操作によって,自動的にさまざまな天体をナビゲーションしてくれます。星図と睨めっこしながら望遠鏡を覗く楽しみもありますが,できるだけ多くの星を手軽に観てみたい。
そんな…、「観る楽しみから入り込んでみたい」。ETXは、このような思いを叶えてくれる望遠鏡です。
■従来までは星の自動追尾=赤道儀でした
天体望遠鏡には、一般的にマウント方式に2種類があります。1つ目は、見たい星の位置へ手で動かし、星の動きに沿って手動で追いかけていく方法。このマウントを「経緯台」と呼びます。経緯台では、星を追尾するためには上下左右のギア操作を手動で行います。
2つ目は、北極星の方向をギアの回転軸と合わせ、地球の自転と逆に動かすことで星を追尾させるマウントです。これを「赤道儀」と呼びます。この方法では、観測する前に地域によって異なる角度(緯度)に傾けておく必要があります。これにより、上下のギアを微動させる必要なく左右のギアだけで星の追尾が可能となります。さらに、赤道儀ではモータードライブと呼ばれる自動追尾を目的とするモーターを搭載することができます。 |
■コンピュータ制御が可能とした経緯台モードの手軽さ
自動導入望遠鏡は、自動追尾を行う従来までのモータードライブの機能を持ちながらコンピュータ制御による自動導入も兼ね揃え、さらに経緯台の持つすぐに観測を始められるという手軽さを持っています。デジタル化が進んだことで比較的低価格化が実現された、デジタル制御な望遠鏡です。
従来までは、赤道儀の場合には北極星が見えなければ星の追尾が困難でした。しかし、自動導入望遠鏡には経緯台モードと呼ばれる動作が用意されており、北極星が見えなくても自宅の庭やベランダなどで一方向の空が開けていれば観測が可能です。このような制御を可能とするためには、基準点と呼ぶ自動導入望遠鏡が動き出す出発点へ正確に合わし、基準星を通常2つ利用して微調整する必要があります。 |
|
|
■ETX-EC(AT)シリーズのおもな特徴
| 1. |
鏡筒が上下左右360度,自在に動く駆動モーターを内蔵している |
| 2. |
オプションの「オートスター」をつなぐと,モーターをコンピュータ制御が可能になり,天体の自動導入が可能になる(注:70ATは標準付属) |
| 3. |
本体が約3.5kgという軽量さ(ETX-90ECの場合) |
| 4. |
洗練されたデザインフォルム(鏡筒のMeadeブルーもきれい) |
| 5. |
意外と見落としがちなのですが、外観の通り三脚は含まれていません。純正三脚か、カメラ三脚を利用します。 |
|
| 上下左右それぞれの駆動モーターを内蔵 |

2つのモーターは独立して動くので,全天のあらゆる位置へ鏡筒を導いてくれます |
ETX-90ECは上下と左右,それぞれに動くDCモーターを内蔵しています。つまり、全天のどこにでも向くことができてオートスターをつなぐことで目的の天体を導入したり、自動追尾をすることができます。
観たい星を選ぶには「オートスター」を操作してメニューから選ぶだけです。基準星を導入した時点で,日時から算出した天体それぞれの位置に望遠鏡(鏡筒)を動かすことができます。操作模様はムービーで用意しています。
駆動するためのバッテリは,底面にセットします。単3乾電池が8本で,約12時間弱の稼働といったところです。 |
|
■自動導入のために動き出すキッカケ
天体自動導入とはいえ,動き始めるための基準点は自分で合わせる必要があります。この点が基準点(ホームポジション)です。 
| オートスターを接続すると天体を自動導入・自動追尾できる |

天体データベースを内蔵しているオートスター |
オプション販売されているオートスターは,14487(30223)個の天体データベースを収録するコンピュータ内蔵のハンドコントローラです(ETX-70ATは比較的データベース数が少ないものの標準付属)。2003年9月以降からは、全モデルが徐々にオートスター標準込みパッケージへと移行していくようです。
電源は,ETX本体に単3乾電池8本を使いますが,バックアップ電源が内蔵されていないので,使うたびに日時の入力を要求されます。これは,常日頃使い続けている中で残念な点の1つです。まぁ,お決まりとして考えれば,そう不自由することではないですが。
オートスターは,惑星をはじめ星団,恒星などを日時から算出し,天球上のどこに位置するかを導いてくれます。オートスターからはじき出された座標計算によって,ETX本体の駆動モーターを動かして目的の位置に動くのです。
|
■気になる光学系、見え方の違いは?
星雲などの見栄えは,初めて眺める人には要注意です。90ECと125ECの見え方の違いをコストパフォーマンスで考えると,個人的には比例しているとは思えません。その差を感じられるのは,覗き慣れている人です。
惑星の見栄えと割り切って期待をするならば,いずれのモデルを選択しても期待を裏切らないはずです。このことは,ETXに限ったことではなく,ほかの望遠鏡の口径差(光学系の違い)でも言えることです。
| 本体は約3.5kgという軽量さ(フィールド三脚を加えると約9kg)、90ECの場合 |

光軸ズレの心配が無いマクストフカセグレン |
口径90mm,焦点距離は1250mmという光学性能を持つETX-90EC。本体の重量は電源の単3乾電池込みで,約3.5kgという軽量さです。ほかのETXシリーズは、後述の仕様表を参考ください。
経緯台モードであれば,三脚も必要することなくベランダなどから手軽に観られます。
しかし,焦点距離のわりに口径が小さいので,星雲などの比較的明るさの暗い天体を観るには適していません。オールマイティな望遠鏡は,基本的にはあり得ません。
ETXは,自動導入と軽量さを兼ね揃えている手軽さがコンセプトです。
|
|
星を観るまでの前準備は,慣れてくると5分以内に終えることができます。
前準備には,まずはETXを地面と水平に保ち,下写真のように,モード別のホームポジションにセットする必要があります(どちらでも選択可能)。動き始めるための基準点をオートスターに教える必要があるわけです。
次に,ETX本体の電源をオンにして,オートスターの基準星セットモードを操作します。この際に入力した日時から算出してその時点で明るい恒星が自動的に選び出されます。鏡筒は自動的に動き出して,対象恒星のおおよその位置へ向きます。
もちろん向いた先には誤差があるので,手で向きを変えたり微妙な位置はオートスターから手動操作を行って,基準星をうまく望遠鏡の視野内に導かせます。
基準性として2つ導入をすることで,ある程度誤差が少なくなって前準備が完了します。さらに,観測中に基準性とするべく幾つかの天体を導入していくと,導入精度が上がります。基準星合わせさえしっかりと行えば,その後はオートスター上でさまざまな天体をメニューから選択できるようになるのです。
M(メシエ)天体であれば番号で入力したり,ガイドツアー機能であれば,日時から選出したおすすめの天体を次々と観ていくことができます。しかし,オートスターの天体データベースは膨大なので,すべてが眼視で観られる物とは限らないんですが…。
ある程度導入精度が高まってきた状態では,自動導入の際には鏡筒が動きだし,標準付属の26mmアイピース(48倍程度)であればほぼ視界内,もしくはその周辺に対象となる天体が近づいています。初めてであれば,その精度に驚き,慣れてくればもっと精度を追求したくなります。
明るい星雲や星団であれば,星図がなくても十分に確認できることでしょう(ホームポジションの精度追求が大切です)。

|
マウント(架台)は,基本的に鏡筒だけを支えるよう設計されているので,過度な重量を加えるのは禁物です。小型ゆえに犠牲になっている点もあるわけです。しかし,私はあえてこの点を覆すべくこだわっているのですが。
■ETXのモデル一覧と仕様
|
・製品別標準価格と発表時期(注:歴代モデル名すべてのリストです。現行モデルは太字の物です)
| 製 品 名 |
国内実売参考価格 |
発 表 時 期 |
| ETX-90RA (通称:Meade ETX) |
自動導入未対応モデル |
1996年 |
| ETX-60ATDX |
正式には国内未発売 |
|
| ETX-70AT |
49,800円
(#494オートスター込み) |
2001年 4月 |
| ETX-90EC |
98,000円
(#497オートスター 別売24,000円) |
1999年 5月 |
| ETX-90EC with UHTC |
2002年11月現在、現行出荷(以降モデル全UHTC仕様に) |
2002年 4月(発売直後USでは上乗せ価格で販売された) |
| ETX-105EC |
128,000円
(#497オートスター 別売24,000円) |
2001年11月 |
| ETX-105EC with UHTC |
2002年11月現在、現行出荷(以降モデル全UHTC仕様に) |
2002年 4月(発売直後USでは上乗せ価格で販売された) |
| ETX-125EC |
158,000円
(#497オートスター 別売24,000円) |
1999年12月 |
| ETX-125EC with UHTC |
2002年11月現在、現行出荷(以降モデル全UHTC仕様に) |
2002年 4月(発売直後USでは上乗せ価格で販売された) |
| ETX-90ECJ |
102,900円(2004年5月現在)
(#497オートスター込み) |
2003年 6月
(日本独自モデル名) |
| ETX-105ECJ |
134,400円(2004年5月現在)
(#497オートスター込み) |
2003年 6月
(日本独自モデル名) |
| ETX-125ECJ |
165,900円(2004年5月現在)
(#497オートスター込み) |
2003年 6月
(日本独自モデル名) |
| ETX-90AT |
(#497オートスター込み) |
2003年 9月(US) |
| ETX-105AT |
(#497オートスター込み) |
2003年 9月(US) |
| ETX-125AT |
(#497オートスター込み) |
2003年 9月(US) |
| ETX-90PE |
(#497オートスター、#884三脚、PC接続ケーブル&ソフト込み) |
2004年11月(US)
2005年6月(日本発売)
|
| ETX-105PE |
(#497オートスター、#884三脚、PC接続ケーブル&ソフト込み) |
2004年11月(US)
2005年6月(日本発売) |
| ETX-125PE |
(#497オートスター、#884三脚、PC接続ケーブル&ソフト込み) |
2004年11月(US)
2005年6月(日本発売) |
| ETX-80AT |
69,300円
(#494オートスター、三脚込み) |
2005年10月(US)
2006年 2月(日本発売) |
|
※2003年9月現在(MIC
STORE価格)、推移としてはRAの次にオートスター別売のECパッケージ、UHTC仕様の登場、そしてオートスター込みのECJ(国内名)、ATパッケージへと変わっています。ATパッケージは、2003年9月上旬段階は国内未発表
・主な仕様比較、各モデルごとの倍率についてはこちら
| |
ETX-70 |
ETX-80 |
ETX-90 |
ETX-105 |
ETX-125 |
| 口径 |
70mm |
80mm |
90mm |
105mm |
125mm |
| 焦点距離 |
350mm |
400mm(バロー:800mm) |
1250mm |
1470mm |
1900mm |
| 口径比[F] |
5.0 |
5.0 |
13.8 |
14 |
15 |
| 光学種別 |
マルチコートアクロマートレンズ |
マルチコートアクロマートレンズ |
マクストフカセグレン |
マクストフカセグレン |
マクストフカセグレン |
| 重量[kg] |
約3.0 |
約3.0 |
約4.0 |
約7.0 |
約8.0 |
| バッテリ |
単3乾電池6本
(DC 9V) |
単3乾電池6本
(DC 9V) |
単3乾電池8本
(DC12V) |
単3乾電池8本
(DC12V) |
単3乾電池8本
(DC12V) |
| 稼動時間 |
連続20時間 |
連続20時間 |
20時間以上 |
20時間以上 |
20時間以上 |
| オートスター |
標準同梱
(#494) |
標準同梱
(#494) |
オプション(EC)、標準同梱(AT、#497) |
オプション(EC)、標準同梱(AT、#497) |
オプション(EC)、標準同梱(AT、#497) |
|
※ どのETXがいいのか? という疑問は、星雲や星団中心であればETX-70AT、惑星を高倍率で見たければETX-90以上がおすすめです。DS-2000は、2070ATがETX-70ATよりも惑星観望寄り、DS-2114ATSは比較的高倍率が出やすいので惑星観望にも適します。見え方の目安は、倍率についてを参考にしてください。 |
身近で扱っているお店が知りたいという人は,ミックインターナショナルのサイト上で,メニュー先の「取扱店一覧」を見ると,日本国内で販売している店舗が分かります。楽天市場を見れば、アクセサリー類も含め数多くの商品がオンライン購入可能です。 
■米Meade Instrumentsの株価
 data:
Yahoo! Finance data:
Yahoo! Finance |
■ETXの歴史 http://www.meade.com/about/

Deep Sky Imager(オートスタースイート、DSI)の国内販売が2月から開始。5月からは、LX-90LNT、ETX-PEシリーズも国内販売。4月には、米国で「ワイヤレス・オートスターII」、「Deep
Sky Imager PRO」の発表。5月28日には、国内総販売元ミックインターナショナル主催の第1回「ミード・ユーザーズミーティング」開催。
Autostar
Suite(オートスタースイート、LPI)の国内販売が2月から開始。ほか、ETX-70ATと並ぶ廉価なDS-2070AT、DS-2114ATSが国内出荷開始。LX-200GPSもSMTモデルへとチェンジ。8月に米国で、AutostarSuiteパッケージのラインアップ拡充として、Deep
Sky Imagerが発表。
10月には、レベルセンサーや磁北極センサー採用の新製品「ETX-90PE/105PE/125PE」が米国発表。LX90-LNTも同時発表。
2003年5月現在、米国では特に動きはありません。依然としてUHTCのアピール、そしてLX200-GPSへのマーケティングが優先されています。そのような中でも、米国では本体価格でオートスターと三脚が付属するキャンペーン、国内では3月1日から8月31日までの限定で本体価格でオートスターを付属するキャンペーンが開催中です。
9月には、パッケージ名変更が行われました。ETX-90EC/105EC/125ECはこれ以降、オートスター込みのパッケージ「ETX-90AT」「ETX-105AT」「ETX-125AT」として展開されていくことに。そして、デジタル先駆者のMeadeとして大きな発表になったのが、Meade
LPI(Meade Autostar Suite)です。
2001年11月には、従来までの硬化プラスチックマウントだったものを「アルミダイキャストに改良」されたモデル「ETX-105EC」が発表され、これを機に従来モデル「ETX-125EC」のマウントもダイキャストに置き換えられています。そして、この年からは上位モデルLX200のオートスター対応が進み出し、搭載メモリ量の多いオートスターII(Autostar
II)の登場、そしてETXの動きは落ち着きを見せました。
これとは別に、ETXよりも低価格な系列モデルとしてラインアップされていたDSシリーズが一新され「DS-2000」シリーズとして2002年3月に発表されています。
さらに,60AT/70ATを除くマクストフカセグレン光学系のETXに関わる、「UHTC」と呼ばれる20%の光学性能アップを実現する発表がありました。鏡のコーティングを変更して性能アップを図ったようです。国内では特に未発表でしたが、2002年11月現在、同一価格にて「with
UHTC」を意識すること無くミックインターナショナルから出荷されています。私は未確認ですが、箱に「UHTC」のロゴがあるそうです(※Shinさんのページに画像が掲載されています)。
2000年になってからは,廉価版オートスター(ETX-ECとは異なる)を搭載する「DS」シリーズ,2001年4月には、低価格な屈折光学モデルの「ETX-70AT」が加わって、自動導入が可能な製品の選択肢は、LX200よりも手軽に扱える製品としてかなり増えました。
日本国内ではETX-ECシリーズとして口径90mmの「ETX-90EC」を1999年5月に発売、口径125mmの「ETX-125EC」が1999年12月に発売されました。私は、6月下旬に90ECを購入し、このサイトを開設することにしました。
ETXは「Meade ETX」(ETX90)として1996年に発売された口径90mmが初のモデルです。後に、ETX-90ECの発売を機に「ETX-90RA」として改名されました。このモデルは、オートスターと接続はできない非自動導入モデルです。 |
ETXシリーズの国内総販売元は、ミックインターナショナルです。同社のページ上からもオンライン手続きで購入ができますが、価格相場はインプレッションページにも書かせていただいたようにほとんど差がありません。
唯一の狙い目とすれば「○○キャンペーン」と題された時期でしょうか。オマケが付くか、アクセサリの優待販売などがあります。 
| 1. |
自分が手軽に持ち運べる重量はどの程度なのか? |
| 2. |
極端な表現であるものの,1週間に数回?1年に1回?どの程度の頻度で観るつもりなのか? |
| 3. |
眼視以外でのデジカメ撮影の用途も求めるのか? |
|
上の3点をよく考えてみて、惑星中心の比較的明るめの星雲星団観望が中心であり、機動性をいちばんに考えたい。そう思える人は、ETXシリーズを選択して後悔がないと思います。私の総括は、このひと言に集約されます。

極めて個人的な見解を書くとすると
ちょこちょこ持ち出せて観られれば,1年に数回としかないシーイングの良い晩に、小口径とは思えないほど細部まで見られる惑星などに出会えます。
LX200クラスの重量は箱から出して野外にセッティングするのでは、上記のタイミングを合わすのはかなり難しいでしょう。それほど、大気の状態に左右されるのも事実です。 |
 |
|
 Google検索  ゲストETXギャラリー新着  時 差 NASA TV 時刻は、02月14日 17:09:49 (EST)です。 太平洋標準時は、02月14日 14:09:49 (PST)です。
 天文用語辞典 - アメリカンサイズ : アイピース(接眼レンズ)取り付け口の径を表したもの。サイズは、31.7mm。ほかに、従来からの国内仕様24.5mm(ドイツ規格)と、2インチ(508mm)がある。
 Advertisement
|


 domain Top
domain Top  Astrophotography
Astrophotography  The Movie
The Movie  News
News  Accessories
Accessories  Link
Link  BBS|ETX
BBS|ETX  About
About
 メニュー
メニュー
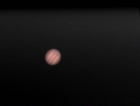

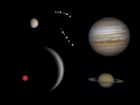
















 Copyright©1999- Yoshi-K All rights reserved.
Copyright©1999- Yoshi-K All rights reserved.